明日が冬至ということと、前日の日記で、クリスマスのお話をアップすることを予告してましたので、一つの小話というかそんなものを載せることにします。
10年ほど前に書いたものを、ほんの少々訂正したものです。
その当時、古い記憶を引っ張り出して書いたものですから、それからの研究や発見があったとしても考慮してはいませんので、現代では間違った解釈があるかもしれませんが、その点はご容赦ください。
僕はキリスト教徒ではありませんが、日本人がクリスマスのことを知ることもいいかなと・・・
何の足しにもなりませんが、雑学程度に(^^;)

-クリスマス考-
12月になりましたね。街は例年通りクリスマスの飾り付けで、賑やかになってきました。
私には普通の日と何ら変わることがないのですが、一部(或いは大多数?)の人たちには意味深な時期が来たみたいです。
ウ~ン、いきなり自嘲気味な書き出し( ̄。 ̄;)
気を取り直し、お約束通りクリスマスのお話をしましょう(^_^)
日本では『クリスマス』とは、イエス・キリストの誕生日と思っている方が多いようですが、本来は『イエス・キリストの降誕を祝う祭日』というもので、キリスト教ではイエスの誕生日とは考えていません。
ではイエスの誕生日は?
聖書には誕生日の記述はありません。いろいろ説がありますが、おおざっぱに春から秋くらいだろうと、推測されています。
根拠として一番もっともらしいものは、イエスの誕生をお祝いに来た羊飼いが、夜の羊の見回りに帰っていったという、聖書の記述あたりでしょうか。
冬には寒いから羊は家屋に入れていたから、夜の見回りは冬にはしない、という理由です。
それでは何故に12月25日を『降誕祭』として祝うようになったのでしょう?
説として、ローマ帝国で信仰されていたミトラ(ミトラス)教の冬至の祭を拝借したとか、ローマの農耕神サトゥルヌスの祝祭が起源だとかあります。サトゥルヌスの祭も冬至の時期にありました。
注目する点は、“冬至”と“ローマ帝国”の二点でしょう。
“冬至”は現在よりも大事な意味を持っていました。太陽はどんどん低くなり、昼間もどんどん短くなる。
『もしかしたら太陽は、このまま低くなり続けるのではないか?消えてしまうのではないか?』
現代人では抱かない不安を、古代人は毎年抱き続けたのです。(冬至の時期は分かっていたでしょうが、“必ず”日が高くなるという保証がなかった。そこまでの科学的根拠がなかったからでしょう)
だから古代人は、太陽がまた高く登りますようにと祈り。そして、太陽がまた高く登り始める“冬至”を喜び祝いました。というよりは、再生を願い祈願した。
日本でも“祭り”は、その賑やかさの裏に“願い”があるように。
ミトラ教では(そして多くの古代宗教において)冬至は一大イベントだったのです。
ミトラ教において“冬至”は、太陽が新しく産まれる。或いは復活する日と信じられていたからです。
そしてローマ帝国。
ご存知の方も多いでしょうが、当初ローマ帝国はキリスト教を(控え目な表現ですが)認めていませんでした。
そんな状況では新しく入ってきた宗教は、ほぼ同じ行動をするように思われます。
既存の宗教との融合です。
日本でも(入ってきた経緯は違うし、意味合いも違いますが)仏教と神道の融合を見ることができます。
表立っての布教ができないキリスト教徒は、太陽の新生(即ち冬至の祭)とキリストの聖誕を結びつけ、共に祝うことでキリスト教に対する垣根を低くした。
キリスト教徒はミトラ教の冬至の祭を取り込むことにより(それ以外にも融合は行われたでしょう)、ローマ市民をキリスト教化していったのでしょう。
結果、ローマ帝国は時代の流れの果て、キリスト教が国教となり、ヨーロッパに広がる盤石の足がかりとなった。と言えるでしょう。
ところでミトラ教って聞いたことあります?
あんまり、というか聞いたことない方が大半でしょう(^_^;)
実は私もよく分かりませんm(_ _)m
まぁ専門家以外詳しく知っている人はいないと思います(^-^;
専門家でも分からないことの多いみたいです(>。<)
起源も古代イラン・インドだろう…といった程度です(^_^;)
信仰の対象は太陽。だから冬至の祭は大事だったのです。
一番盛んだったと思われる時期は、古代ローマ帝国で、紀元前一世紀から紀元五世紀くらいまで。主に下層階級で信仰されていました。
ここは重要です。
何故ならば、下層階級の人口が一番多かったからです。
キリスト教を広めるためには、ミトラ教徒を取り込むことが近道でしょうし、それなくしてローマ帝国の国教には、なり得なかったでしょう。
ミトラ教は仏教にも影響を与えていた、とする研究者もいます。
ミトラ=マイトレーヤ(弥勒)
さて、前頁までは『クリスマス』の起源を、ざっと(^。^;)辿りました。
悠長に書いていると、イヴになるかもしれない(・・;)
イヴ…そう!クリスマスといえばイヴがメインですね!!多少強引?
皆さんは『イヴ』の意味を、どう捉えてます?
年配の方は『前夜』と思っている人が多いのでは?
なんせ、24日の夜にケーキ食べますもんね(^_^)
では、何で24日の夜なのか?クリスマスは25日なのに、なんで?
これにはキリスト教の『教会暦』が関係しています。
起源はユダヤ教暦といわれますが、要は教会で使う暦。そのまんまですね(^。^;)
ここで大事なのは『教会暦』では、日没が一日の始まり。となっていることです。
なんで?
はい、もっともな疑問です(^^)
ここで皆さん、紀元前の農民になって下さい(>o<)
あなたは一日が24時間であることも、ましてや時計の存在も知りません。
そんなあなたは、日が昇ったら畑に作業しに行きます。夕日が沈む頃、家に帰ります。
あなたにとって、一日の始まりは?一日の終わりは?
この答には2つの考え方があります。
一つは“日の出”
日が出たときが、一日の始まり。よって日が出たときが、一日(前日)の終わり。
もう一つは“日の入り”
日が沈んだときが、一日の終わり。よって(お分かりですね)日が沈んだときが、一日の始まり。
日の出を基準とした例は、初夢でしょうか。
1月1日の、日の出が一日の始まりとすると、新年になってから見る夢は…分かりますね(^o^)
日の出までは、“前年”です。
だから元日の日没から二日の朝が、新年の初めての夜となります。
初夢をもう少し言うなら、二日以降に見た夢のことを指します。
ですから、二日の朝に夢を見なかったとしても、それ以降に新年の初めての夢を見たら、それが初夢です。
そして“日の入り”を基準としたのが、そうです『教会暦』です。
ですから24日の日没から25日が始まり、25日の夜(クリスマスイヴ)となり、25日の日没でクリスマスは終わります(^^)/
なぜ日の入りを基準としたかは、はっきりした理由はわかりません。
何故ならば、その起源があまりにも古すぎる習慣の一つだからでしょう。
推測するとしたら。
太陽が西に沈むことは、太陽の“死”であり、そして再生し、太陽が東から昇ってきた時が“新生”したと考えた、古代エジプト人。
“死”と同時に“再生”が始まると考えた。その思想の影響ではないかと、個人的には思ったりします。
追記
正教会の幾つかの教会では、いまだユリウス暦を使っている教会もあり、そこでは私たちが使う暦の1月7日がクリスマスになっています。
ちなみにキリスト教では、『クリスマス』より『復活祭』の方が重要視されます。
教皇ベネディクト16世の言葉
……クリスマスはとても楽しいが、同時に深く内省すべき時でもある。私たちはつつましく貧しい馬小屋の光景から何を学べるだろう。
日本で初めてクリスマスが行われたのは、1552年(天文21年)周防国山口(現山口市)だそうです。宣教師のコスメ・デ・トーレスが付近の信者を集めて行ったという記録があるそうです。
一日の始まりのお話。『教会暦』をご存知の方はたくさんいらっしゃると思いますが、根源はもっと古く、生活に密接したものです。そしてこれは古代人の認識の限界、現代日本人の認識の相違と言えるかもしれません。
皆さんが良いクリスマスを、迎えられますように(*⌒▽⌒*)
私は、私は……?
フッ(;¬_¬)
と、前年まではなっていましたが・・・今年は!!
そうです!今年はアルが居てくれているのです(^O^)/
アルー、アルー、もうすぐクリスマスだよ(=^・^=)・・・アルー・・・寝てる(;一_一)
きっと『ちゅーるてんこ盛り』の夢でも見てるのかな(*^-^*)
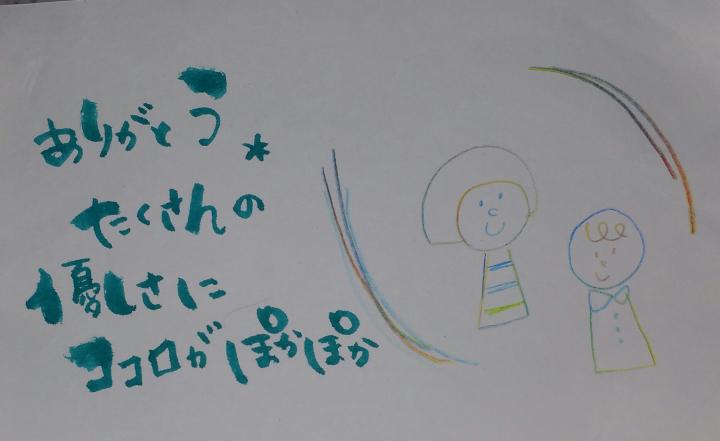


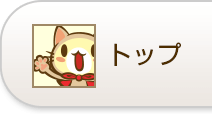
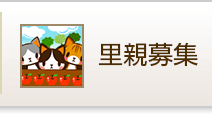
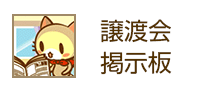


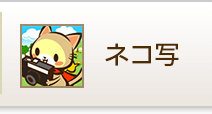
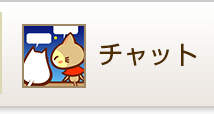
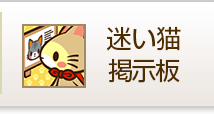
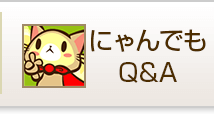
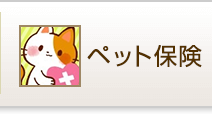
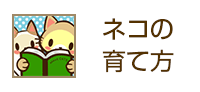
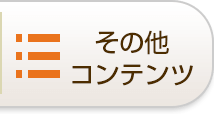
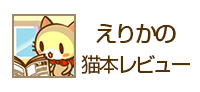




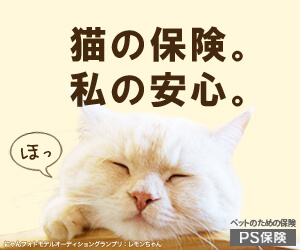




































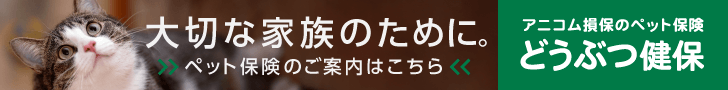









 35
35
最近のコメント