
全国各地で繰り広げられる「殺処分ゼロ」運動。
我が徳島県でも、かなり積極的に取り組んでいます。
その一環として、年に一度開催される『動物愛護セミナー』。
この数年は愛護に関心の高いタレントを呼んでましたが、
今年は一転してNPOや行政の担当官がトークゲストとして参加していました。
会場には空席が目立ちましたが、今までよりもひとつレベルの高い会になっていたと感じました。
会の趣旨として、多様な価値観を認め合う『ダイバーシティ』といったキーワードがあったのでしょう。
愛護活動に携わる民間、行政、中間支援組織やNPO等のステークホルダーが、様々な「考え方」で活動を展開している中、いくつものトラブルが発生している現状があり、そこを調整しないことには先に進んでいけない、そんな局面が間近に迫っているからかもしれません。
その上で、一昨年に改正された『動愛法』には、今まで日本であった『動物愛護』とは違った観点からの『動物福祉』というものが加わっています。
実は動物愛護と動物福祉の考え方には、相容れない部分があって、それが法としての整合性を欠く原因にもなっています。
(議員立法なので法の専門家が作成したわけではない…ってあたりも一因)
例えば、
ニンゲン以外の動物に対する考え方は
・動物愛護→生命あるもので、天寿を全うさせるべきもの→終生飼養は努力義務。
・動物福祉→意識あるもので、苦痛を与えないことが最上→安楽死も選択肢の一つ。終生飼養は義務ではない。
といったもの。前者は日本的な考え方で、後者は西洋の考え方です。
この考え方の差で最も違和感を抱くだろう例としては、
保護シェルターで「ノー・キル」と謳っているところ。(アメリカでは約8割がそう)
これは「私たちはけっして死なせない!」と言っているわけではありません。
矯正不能だったり、老齢や病気などで引取が見込めない(譲渡できない)と、判断された動物『以外』は生かします、といった意味です。
(ので、安楽死は肯定します)
法は、その国あるいはコミュニティで生活する人間たちが、
いかにすれば『幸福に暮らせるか』を基準とし成文化させ約束と同意を取り付けたものです。
だから国が違えば、当然法も違います。
一国としての普遍性は有しても、グローバリゼイションの中では、日本の考え方は、とてもマイナーなものです。
だからこそ『動物福祉』の考え方が、動愛法にも反映されたのでしょう。
環境省から来られたゲストが、
こういう状況に日本はある中で、結局『他者にたいする寛容さ』で、うまいこと調整してやっていくしかないのでは?とおっしゃっていましたが、私もそう感じます。
寛容さとは、イイカゲンさとも言い換えられます。
それは「Yes/No」をハッキリ言わない文化を持った日本人の得意技かもしれませんしね。

↑もっとも、君たちが話せれば、こういう問題はすべて解決するんだろうね


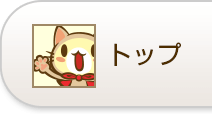
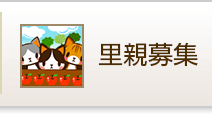
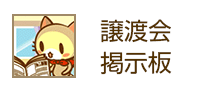


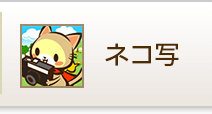
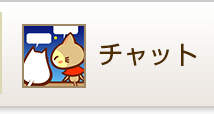
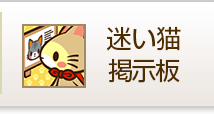
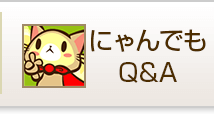
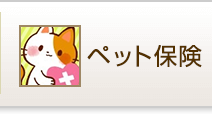
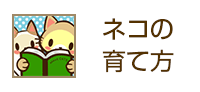
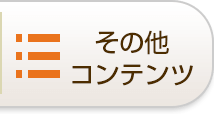
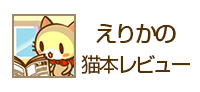




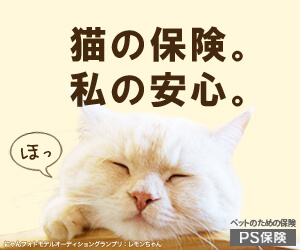













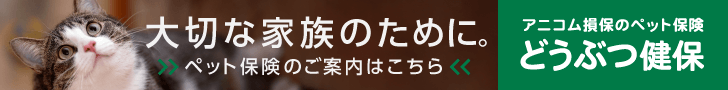
 30
30
最近のコメント