海ガメの生態などを学び、その後、海に行って海ガメを放流するというものです。

先ずは、簡単に海ガメの生態と種子島での産卵のための上陸頭数、その回数などを、種子島で一番古い古民家である古市家住宅にて講義です。

ちなみに、古市家住宅は江戸時代の末期に建造された古民家です。
当時の庄屋の家らしく、柱の下に銅板を敷くなど意匠が施されていて、かなりの権力を持っていた方のようです。
もっとも、国の重要文化財に指定されたことで、建物自体は柱などの再利用は多いものの再建されています。
なぜか、この日のために、火縄銃や甲冑なども展示されていて、ちょっと興奮しました‼️

そして、講義とビデオ上映の後、海へ移動です。
放流する海ガメは、バケツに入れられていて、今か今かと海への帰還を待ち焦がれるように手足を動かしていました。
この海ガメたちは、講師の先生が卵から孵って、海に帰れなかった海ガメを保護されたものです。
孵化しても、砂浜深くにいた場合は、産卵場所の砂浜を這い上がることのできない子たちもいるんです。
先生は、そんな人の手を貸さないと助からない子たちを保護されているんです。
頭が下がります。
体長、約7・5センチほどのチビ亀たち
一見すると、縁日のミドリ亀のようでもありますが、頭の大きさが決定的に違います。
海ガメの方が頭が大きいようです。
小さなお子さんとその保護者に交じる自分
参加人数は20人でしたが、小さなお子さんも多く、制限人数以上はいそうですが、先生も30匹ほど用意されていて、無事に一人一匹は確保されていました。
さぁ、海への放流です。

参加者全員で、横一列に並び、一斉にチビ亀たちを海に放します。
ジタバタと必死に海に向かって、手足を動かすチビ亀たち
本能として、母なる海に帰ろうとしているんですね。
感動しました‼️😂⤴️⤴️
ところで、この海に帰ったチビ亀たちが、この巣だった砂浜の海に戻るのは、40年と言う長い年月を要します。
そして、無事に産まれた砂浜に帰ってこれるのは、5000匹に一匹と言われています。
海鳥や大型の魚に補食されず、長い長い海での生活を経て、故郷の砂浜に戻るまで成長するためには、過酷な生存競争を生き抜かないといけないんですね。
この広い大海原を自由に泳ぎ、たくましく生きて、40年後に大きくなって帰ってこいよ‼️😂
午後1時からの短い時間でしたが、貴重な体験ができました。
きっと離島ならではの体験です。
海の綺麗な種子島ならではの体験です。
この海ガメの出産する砂浜を守らないといけないですね。
最近のぎんちゃんとしーちゃんの近況

本当に緩やかではありますが、一歩一歩、互いの距離が近付いているようです。
まだまだ、しーちゃんが、ぎんちゃんにビビっているような感じらしいです。
でも、ぎんちゃんも、しーちゃんが元気に動くと追いかけたくなるらしく、依然として縄張り意識が強いのかなって感じらしいです。
でも、それでいいんです。
まだ2週間ですから
一月、いや、二月でも三月でもいい。
ゆっくり仲良くなって欲しいです。
ぎんちゃんもしーちゃんも家族だから
大切な大切な家族の一員だからね🎵😄
と言うわけで、最後まで長文にお付き合い、ありがとうございました‼️😂⤴️⤴️


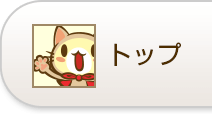
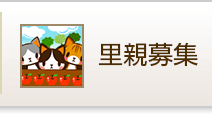
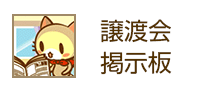


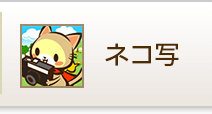
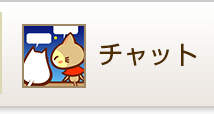
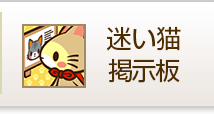
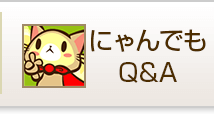
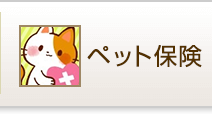
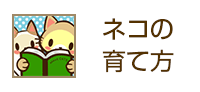
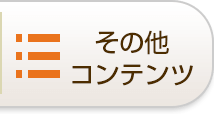
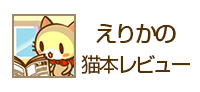




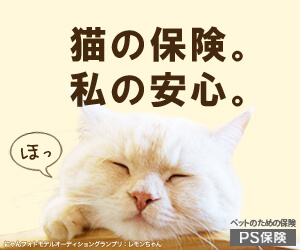













































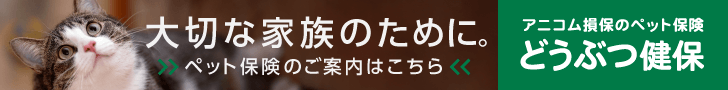
 43
43
最近のコメント