但し、行き先はとてもローカルで地味な所です。
7月の終わりは「東海道関宿」
関宿は、東海道53次の江戸から数えて47番目の宿場町で参勤交代や伊勢参りの人々で賑わった町です。
現在、旧東海道の宿場町のほとんどが旧態をとどめていない中で唯一歴史的な町並みが残っています。

左は、京都・大津方面に向かっての町並み
右は築230年たった、旦那の同僚宅。
玄関にチラリと見える物は、旦那のお店の商品。
今回、観光客相手にテスト的に販売してみたそうです。
東西に続く1.8kmの街道は国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されており、写真のような古い家が200件ほど残っています。
銀行、郵便局なども、風情を壊さない渋い造りになっており、もちろんコンビニはありません^O^自販機の数もかなりおさえているようでした。
江戸時代後期の町・・・とまではいきませんが、思ったよりもその渋さが素敵に感じられ、「年とったんだなぁ(((^_^;))なんて思いました。
ただ、素敵に思っても、ここで生活することは、この古い家を維持していくことは、かなりたいへんだと感じました。実際に、玄関の柵だけは渋い造りで、その奥には、○○ハウス的な建物が・・・(^m^)
この日は年に一度の夏祭りの日です。祭りは午後から開始で夜がメイン。
まだ、昼前で観光客は少なく、山車の準備をしてるようでした。

左は、「関の山」の語源になった山車です。
その昔、関町から京都の八坂神社の祇園際に出される山車は、たいへん立派でこれ以上の山車は作れないだろうと言われた為、精一杯の限度を「関の山」というようになったそうです。(雑学ですね(^-^))
右上は、ミニ山車。写真下のように小さい子供達が、各家にあるミニ山車を引く姿がとても可愛らしかった(^∀^)ノおそらく、夜にはハッピ着て、沢山の子供達がミニ山車を引き歩くのでしょうね(*≧∀≦*)
また、機会があったら夜に来たいと思わせる風景でした。(やっぱり年とったな(^_^;)(^_^;))
********************************************************************
8月頭の土曜は、三重群菰野町にある「パラミタミュージアム」なる所へ。
館名の「paramita・パラミタ」は梵語の「はらみった・波羅蜜多(迷いの世界である現実から悟りの境地である涅槃に至ること)」からの由来だそうです。
般若心経の初めにありますね。
この日は小ギャラリーで「蓑虫(みのむし)の切り絵展、熊野の自然と伝説」の展示に。
蓑虫さんは、旦那の取引先の関係者の方で、店に蓑虫さんの作品もあるところから行っておきたかったようです。
もの凄く精密で細かい切り絵に、またアニメちっくな作品もあり楽しませて頂きました^^
他の常設・企画展も周りました。
内容は・・・・割愛させて下さい(((((((・・;)
仏師、長快作の鎌倉時代のすばらしい観音像には感動しましたが・・・後は、芸術が爆発していて、凡人には理解できないものでした(@_@)
片岡鶴太郎さんの企画展で、「ホッ」とさせて頂いて、結局、鶴ちゃんの作品からのネコグッズを買って帰りました(~▽~@)♪♪♪

クリアーファイルとエコバックです。
やはり最後はここに落ち着く私です(*^ー^*)v


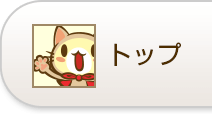
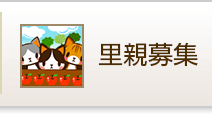
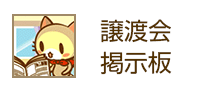


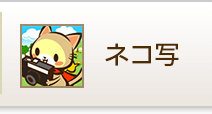
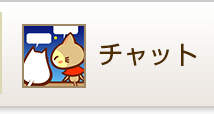
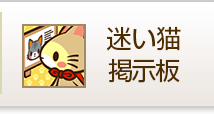
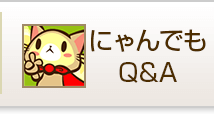
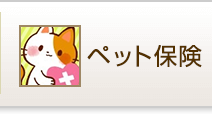
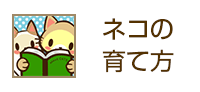
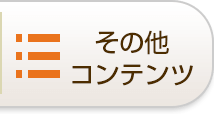
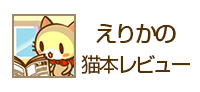




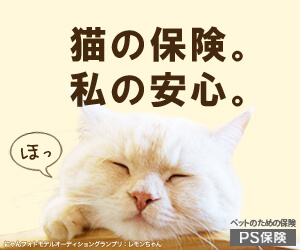


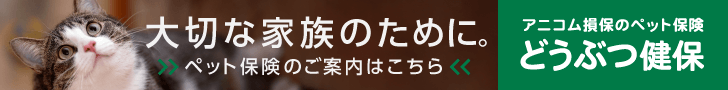
 1
1
最近のコメント