今年は杉本彩さんを基調講演にお招きし・・・
という話だったので、
会場がグレードアップしてました(笑)

↑イベントのフライヤー
良くも悪くも、芸能人は目立つので、
愛護に関心なくとも、来場された方もいるでしょう。
けど、
これって、かなり重要だなぁと感じました。
愛護のイベントって、愛護に既に関心があったり、
取り組まれてる方が集まるので、
自家中毒に陥りがち。
だから、新しい人を呼び込む訴求力が弱い。
芸能人の取り組みは、
その問題を乗り越える力があるなぁと、感じました。

↑パネルディスカッションの様子
初めて拝聴した、杉本さんのお話は、
動物愛護を取り巻く様々な問題を、
短い時間の中、うまくまとめられ、
たいへん情熱的で、
心打たれるものがありました。
彼女の話の中で、
私も思い当たることがあったのは、
「動物愛護とは特別な人が行う、特別なことではない」
「いのちの問題であるからこそ、人としての資質が問われる」
「愛護≦共生」
というメッセージでした。
私も、乞われて愛護イベントの
広報物を作ることがあります。
その中で、いつも「愛護」という言葉の壁を感じています。
(ここでいう愛護は、むしろ管理を意味することが多い)
ニュアンスとして、堅いんですよね。
「だから愛護しなさい」的な、プレッシャーを感じてしまう。
様々な愛護活動の在り方の中で、
その発端は、動物が「好き」という気持ちだと思います。
そこから、困難に直面している動物がいたら
A.助ける
B.(結果的に)助けない
という選択肢があって、
いづれを選ぶかは個々人の、その時の状況の問題。
気持ちの強さだったり、環境的な余裕だったり。
だから、
最もミニマルな愛護活動とは、
自分と共に住んでるパートナーを、
最期まで看取ることなんじゃないかなぁと。
そういうことを愛護とは言わないけれど、
本筋として、異なるところはない気がしています。
それらをつなげる言葉が生まれたら、
もっと色んな方が、参与されるんじゃないかと、
もっとカジュアルになるんじゃないかと考えています。
裾野を広げないと、致死処分ゼロなんて目標は、
達成できるものでもないと思うので。

↑他者を思いやる気持ちと、想像力が大切ですね
致死処分ゼロに関して、
まだまだ問題は山積みですが、
ローコストで何とかなる方法を考えたいです。
例えば、
小学校/中学校で授業として、
1年に1時間だけ時間を割いていただくこと。
また環境省の担当者が、
各地方のセンター/保健所への抜き打ち訪問を行い、
動愛法の適切な運用がされているかの、確認を行うこと。
この2つを実施していただければ、
ずいぶん弾みはつくんじゃないかなぁと、思っています。
あらゆる社会問題解決の第一歩は、
「知る」ことから。
また、行政には弱い事業のPDCAサイクルを強化することが、
今後ますます必要でしょう。
(Checkは議員を代表とした住民の機能でもありますが・・・)


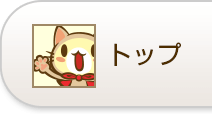
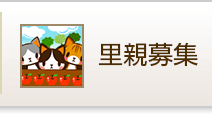
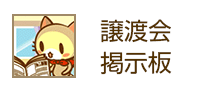


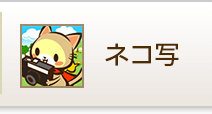
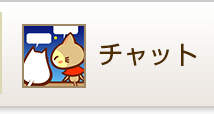
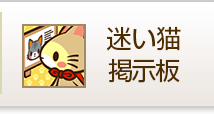
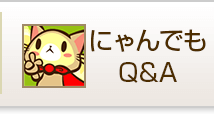
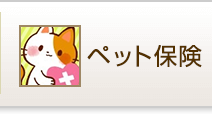
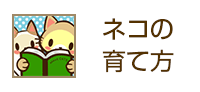
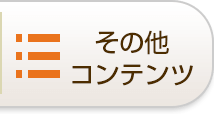
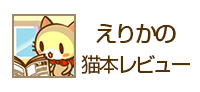




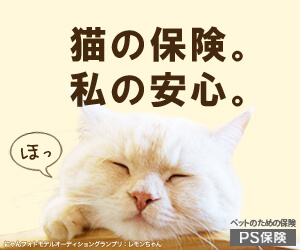


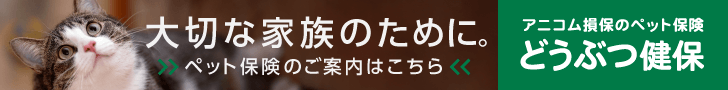
 30
30
最近のコメント