県主催の「動物ボランティア意見交換会」
に参加してきました🙂

参加者は団体さんや個人ボランティアだけではなく、ボランティアに興味のある個人も参加されていました。
まず、行政から1年間の、
①飼い主責任の徹底化
②人と動物の安全と健康の確保
③地域活動の充実
として、数値含めた報告や情報提供がありました。
①では、県内保健所に持ち込まれた犬猫の
保護数から殺処分数などの報告があります。
静岡県の保健所では、飼い主からの持ち込みに関しては、終生飼養・殺処分回避の観点から、
引き取りをまず断り、
飼い主による次の飼い主さん(里親)探しを促します。
場合によっては、保健所から登録ボランティアさんを紹介・仲介・協力依頼もしているそうです。
犬の殺処分に関しては、
平成26年は181頭だったものが、
平成30年には17頭まで減少しています。
猫に関しては、

右肩下がりではありますが、
殺処分に関し、
まだまだ犬の様には立ち行かない現状があります。
猫の殺処分数、
平成29年は738頭、
平成30年が527頭。
211頭減ったとはいえ、犬とは比べ物にならない数値になっています。
猫の殺処分数には、飼い主不明で持ち込まれた子猫が、そのまま保健所で病死してしまった数も含まれています。
又、猫の殺処分数の9割以上が、
「飼い主不明の猫」であり、内訳も「子猫」が圧倒的に多い現状があります。
私の所管の保健所では、殺処分回避の観点から、野良猫(飼い主不明の猫)の引き取りも、基本的に断る姿勢で取り組みをしています。
県の職員から、
「猫の殺処分を一匹でも多く減らしたいです!」
と、無機質ではなく、気持ちのあるコメントも有りました。
それはそうだと思いました。
県の職員だって、好き好んで「殺処分」する訳ではありません。
助けてあげたくても、引き取って1日も持たず、病死してしまう子猫を看取るのことも辛いと思います。
私達のような一般の飼い主が、
猫の殺処分数を減らす、無くす為に、
何が出来るのだろうか?
県の職員の「生の声」に触れ、
改めて考えさせられました。

飼い主のいない猫の殺処分回避、及び繁殖防止の為に、
静岡県では令和元年より、
TNR助成金が、金額に差はあれど、
全市町に導入されたことの報告もありました。

②の項目で、
猫の問題として、「苦情件数」の話がありました
。
犬の苦情件数は減少しているのに、
猫の苦情件数が毎年増加し、
苦情件数としては横ばいになっている現状があります。
悲しいことですよね。

猫による苦情に関しては、
飼い主のいない猫だけの話ではありません。
「放し飼いの猫」の苦情も含まれています。
静岡県では、今後も、
「完全室内飼養」「繁殖制限措置」に力を入れていく報告がありました。
動物ボランティア側のパネリストさんの話の中で、
猫の殺処分が減らない・無くならない要因として、
個人・団体問わず、
「譲渡後の追跡調査をしていない」
「追跡調査が不十分」
という話が有りました。
確かに環境省の「譲渡推進」のPDFにも、
「譲渡後の追跡調査の必要性」
が書かれています。
飼い主が見つかって良かった!
で終わるのではなく、
譲渡した個体が、その後、
「ちゃんと室内飼養されているか?」
「避妊去勢が適切にされているか?」
を確認していくことも、やはり大切だなと
思いました。
ボランティア側のパネリストさんから、
「猫の問題を解決するには、適切な避妊去勢・完全室内飼育が必須」
な話に、長年動物愛護活動されてきた重みを感じさせられました。
私の参加している意見交換会では、
県の職員、参加者が輪になって意見交換もするのですが、
今年のテーマは「被災動物の対応」についてでした。
「同行避難」と「同伴避難」は違う訳ですが、
猫の場合、避難自体が難しい場合も少なくは無いので、
「自助が大切になる」話がありました。
日頃からの、フードなどの備蓄や、
避難が難しい場合、自宅の耐震化や家具の固定など、やれることをやっておくことの大切さの意見もありました。
又、情報提供の中で、
マイクロチップの飼い主責任として、
「情報変更の義務」が飼い主に課せられる話や、
「化製場法」の話も有りました。
化製場法に関しては、法律自体には猫は含まれてないのですが、
都道府県・市区町村によっては、付随や条例として、
住宅地で猫を飼う場合、一定数を越える時は、一般の飼い主でも、
市区町村に申請許可を受けないとならない所もあるので、
そこは気になった方は各自確認してみて下さいね。
長い日記になりました。
動物ボランティア意見交換会は、こんな感じで色々な話も出来て、知ることも出来ます。
私も一般の飼い主に近い存在での参加ですが、興味が湧いた方は、是非参加してみて下さい。


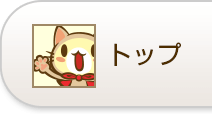
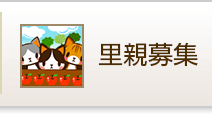
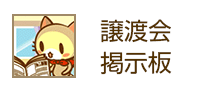


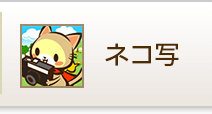
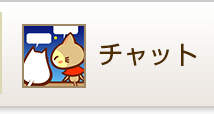
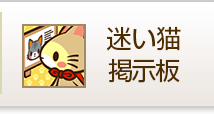
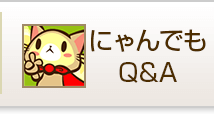
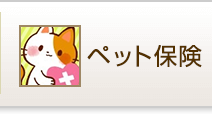
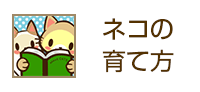
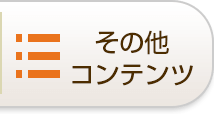
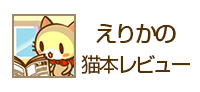




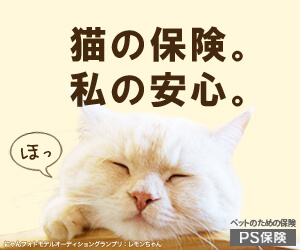




























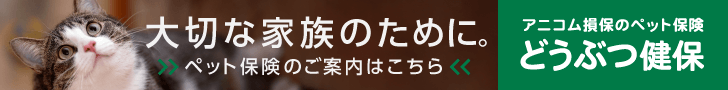
 31
31
最近のコメント