親バカな私は早速、写真アップします。

「試合が終わった瞬間から次の試合の準備ははじまっている。マルリンピック、マルリンピック、この桶ちょっと大きいぞ、丸くなれないよ」
「しぢゅちゃん、それはタライだよ、プールみたいだね。」

「まにゃちゃん、今度は一緒に丸まろうね。」

「まにゃちゃんにイヤっていわれました~ぁ。こうやって、こうやって、ひとりで練習しま~す。」
志づが入っているのは漬物にする冬野菜を洗うタライです。
もちろん漬物を作るのは母です。
西の京都、東の山形といわれるほどたくさんの種類がありますが、今回はたくあんと青菜を漬けたようです。
青菜(せいさい)とは高菜と野沢菜を混ぜたような野菜で辛くて、苦くて、漬物以外では食べられません。
その家々で塩などの配合が受け継がれているのか、未だに青菜を量るときは一束(いっそく)一貫目(約4kg)の単位です。
青菜を細かく切って大根やにんじんと一緒に漬けたおみ漬けというのもあります。もともとは山形を訪れた近江商人が落ちた葉っぱや屑として捨てるところをもったいないと漬けたのがはじまりといいます。
山形市の隣の上山市に春雨庵といういおりがあります。たくあん漬けの考案者、沢庵和尚が徳川幕府のいうことを聞かず、ここに流されて4年間暮らしたそうです。
長い冬に備えて、漬物づくしの山形、塩分の摂りすぎで高血圧の人が多い県です。
って、また話が反れました。


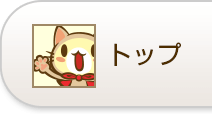
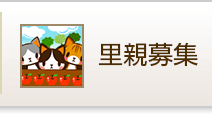
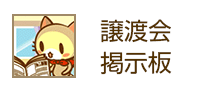


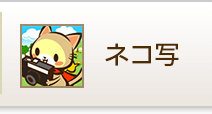
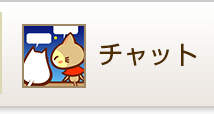
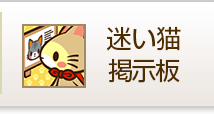
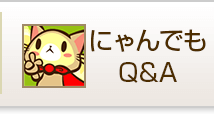
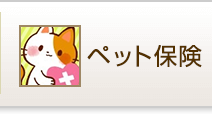
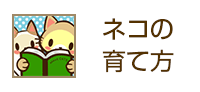
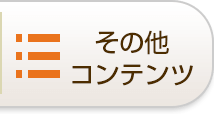
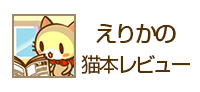




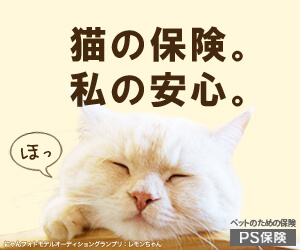




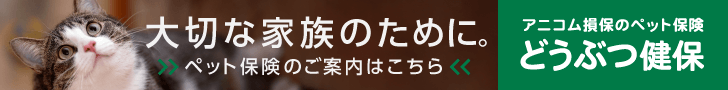




 26
26
最近のコメント