小難しい画材の話から始まりま~す(^o^ゞ
油絵具がチューブになる前は、ヨーロッパでも手作りで絵の具を練っていました。
チューブが開発され、屋外に持ち歩くことができるようになり
写生しながら油絵具で描くこともできるようになりました。
日本は、古来から自然素材を砕き粉にしたものに
動物から煮出した淡白質のニカワを接着剤にし
水で濃度を調整しながら絵の具としてきました。
神社仏閣で彩色された色彩を思い浮かべていただけると
群青(岩石)、緑青(岩石)、朱(岩石)、黄土(土)、白(胡粉ごふん)、黒(墨)
そこに、金箔、銀箔。
くらいしかないですよね~
岩を砕き作った絵の具なので、岩絵具と言います。
人工的に作った絵の具は、新岩絵具と言われています。
写真の上、人工的に作作った新岩絵具。
今ではどんな色でもあります。
絵の具屋さんにいくと、風邪薬の瓶に似た色々な大きさの瓶が棚にずらずら並ぶ中
量り売りで購入するのですが、ま~見てるだけでも楽しい(*^▽^*)
新岩絵具は安価ですが、天然岩絵の具はグラム万単位もあります。
一番下に原石、砕いた絵の具は石そのままの色ですよね(^∇^)
天然岩絵具は、大事に使ってます。
いまは、原石が枯渇してきています。
貴重な天然岩絵具、中でも極上の岩絵具が作られると
文化勲章級の画家に売られるようです。
一般人は、お目にかかることもないらしいです。
まあ、高価過ぎてまず買えませんが(笑)

この、ガラス瓶、可愛くないですか?(笑)
コルク栓がいいでしょ♪
もうすぐ30年~~
日本画を専攻し、大学で一番最初に手にした全員同じ岩絵の具。
今、この瓶では売ってくれないのでは?


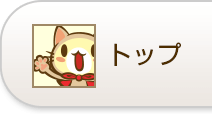
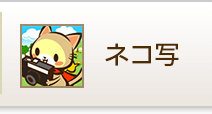

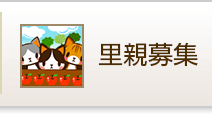
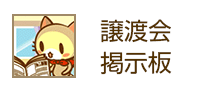


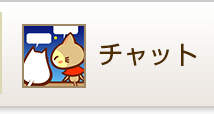
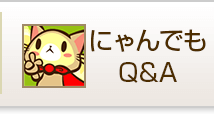
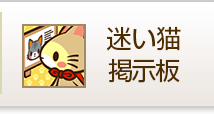
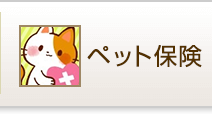
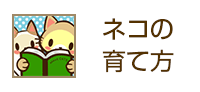
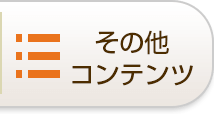

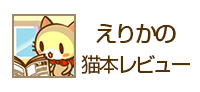
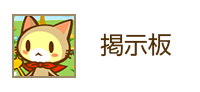




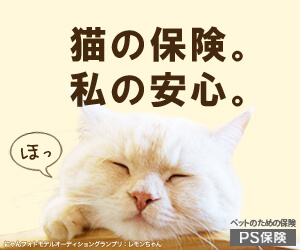













 36
36
最近のコメント