今、大学は至れり尽くせりだとか。
30年前は、ほったらかし(^o^ゞ
自由といえば自由、何でも自力(笑)
技術も自分で探り出す、ひたすら試行錯誤でした。
展覧会にいけば、間近で絵を凝視(笑)
どんな絵の具をどんな重ね方してるか見る。
有名な日本画家の作品を間近で見てみてください!
筆をどう運んだか分からないし
絵の具をどんな重ね方してるかなんてまるで、秘技(笑)
初心者は、ニカワが滲む、水が滲む、筆が丸見え
絵の具の重ね方が悪く色が殺し合いくすむ。
油絵は乾けばいくらでも描き重ね隠すこともできますが
日本画は粒の重なり、最初の躓きが最後まで影響することもあります。
どうしても、技術が身に付かない場合は
描きたいように描けないジレンマでリタイアすることになります。
技法書からです。

1つのお皿に1つの色を作ります。
胡粉のときと同じで、指で絵の具とニカワを練り水で調整します。
以前、梅雨どきに、日本画を教えていた生徒さんで
お皿の中で練る過程でニカワが腐ってしまう人がいました。
困りました(>_<)
同じ粒の大きさの絵の具なら、だいたい混ざり合うのですが
比重が違うと沈殿して混ざらないこともあるので
混色は経験が必要です。
あっ、完成に近づくと筆は片手に2本持つことが多く
絵の具を含ませた筆で描いては、水だけを含ませた筆でなじませるを繰り返します。


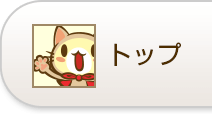
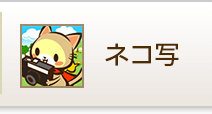

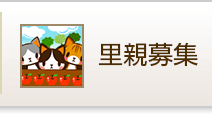
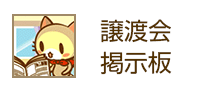


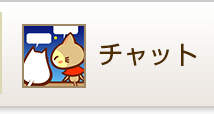
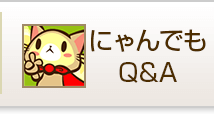
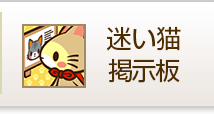
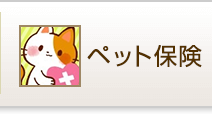
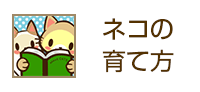
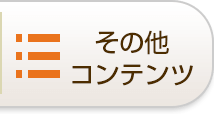

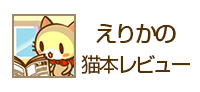
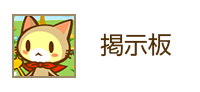




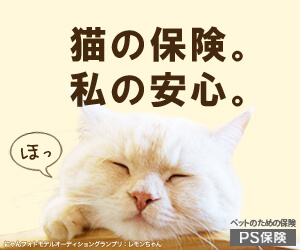













 36
36
最近のコメント