平安時代に創建(そうけん)され、南北朝時代に吉野で四年間過ごされ
後醍醐天皇(ごだいごてんのう)の勅願寺(ちょくがんじ)と定められました。
※勅願寺とは、時の天皇・上皇の発願により、国家鎮護・皇室繁栄などを祈願して創建された祈願寺のことです。
元々あったお寺が勅願寺となる場合もあるみたいです。
醍醐天皇は如意輪寺に足しげく通われ
本堂内で僧が読経の最中に参拝に訪れた天皇が邪魔(じゃま)をしないようにと
外で腰かけてお待ちになられたという腰掛け石が残されています。
毎年秋、後醍醐天皇が自ら鑿(のみ)を入れたという木像が安直(あんち)される御霊殿(ごれいでん)のご開扉(かいひ)が行われてきましたが
後醍醐天皇即位700年の節目にあたる今年は
御霊殿内陣が特別に公開されています。
雑誌で見つけ行きたい!!
え??たった4日間、1日10名。
電話するとやはり、、、予約でいっぱい。
キャンセル待ちになりました。
数日後\(^o^)/やったー♪♪

ご住職のお話
吉野は戦火でほとんどの寺が焼かれました。
如意輪寺は焼けなかったので
天皇の木像や楠正行(くすのきまさつら)が辞世の句を鏃(やじり)で書いた扉などが残ったらしいです。
☆南朝御所(なんちょうごしょ)などは如意輪寺から中千本と言われてる谷の向かい
金峯山寺(きんぷせんじ)がある辺りにありました。
だから焼かれなかったのかな?
そのあとは衰退し寺は荒れ…。
江戸末期?明治に入りたくさんあった寺が
廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)で取り壊しになるなか
小松院というお寺の美しい装飾部分を再利用し
増築されたそうです。
御霊殿の内部は撮影禁止。
建物は入り口の彫刻です!

撮影禁止のため、雑誌より(*´艸`*)
奥に後醍醐天皇が鑿を入れられた木像があります。
仏師がお姿に似せて彫刻し、最後に天皇ご自身が
一鑿(ひとのみ)入れられたんじゃないかと言われてました。

奥の木像が安直されている天井に54枚の花絵があります。
須弥檀(しゅみだん)まで上がらせてもらい懐中電灯でじっくり
見せてもらえました!
なかなか大胆な筆使いの花絵でした。

東大阪の四条にある往生院(おうじょういん)を本陣にした南朝、大将楠正行(くすのきまさつらは、楠木正成まさしげの長男)。
河内の地を理解しつくしたゲリラ作戦で連勝してきた正行。
全国から集められた北朝軍に遂には…
最期の戦いと悟り、吉野の後醍醐天皇にご挨拶に…
※ちょっと調べます!後醍醐天皇か後村上天皇か。
如意輪寺には、一緒に戦う143名の髪を埋め
辞世の句を扉に鏃(やじり)で書とめ出陣していきました。
父正成と大阪の島本町、桜井で別れた11歳。
遺言を守り23歳で亡くなります。
かへらじとかねて思へば梓弓なき数にいる名をぞとどむる(太平記)
【通釈】生きては還るまいと予め決心したから、鬼籍に入る我らの名をここに書き留めるのである。
【語釈】◇梓弓 「いる」の枕詞として用いるが、また武器の名を出すことによって、書き留める「名」が兵(つわもの)の名であることや、戦場に向かう決意などが暗示される。◇いる 射る・入るの掛詞。

楠正成(大楠公)、嫡男正行(小楠公)
我利益の戦いは一度もしなかったことで
いまでもたくさんの人に愛され
史跡や縁のある場所を皆さんが大事に守り
慕われているだな~と思いました。


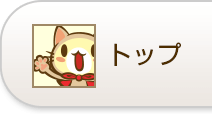
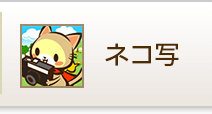

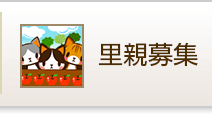
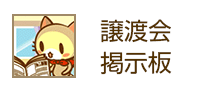


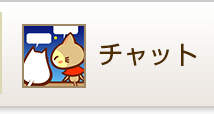
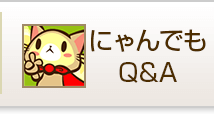
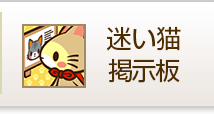
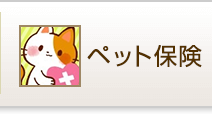
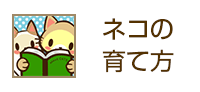
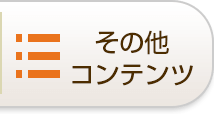

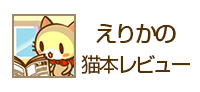
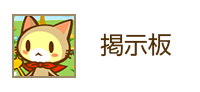




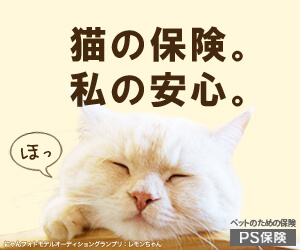






























 36
36
最近のコメント