
最近、御無沙汰が続いています。
小さい頭で考察してみました。
なぜに日記の更新が出来ないのかを。
寒くなり主は外でのライニングをささぼりがちです。
日記で読んだ猫ちゃんを思い浮かべてながら、頭を真っ白にして走っていると歌が出来るのだそうです。
そうです、最近走らないから、歌が詠めないのです。
そんな、僕の日記も閲覧履歴だけは増えています。
とっても勇気を与えてもらっています。
もう一つ大きな訳が。
皆様に公表した、公募落選の事が尾を引いているのです。
いえいえ、悪いほうにではなくポジティブな感覚で。
いつか必ず通過できるようにとただ今、鍛錬中みたいです。
そこで、この場を借りて他サイトで公開した作品を載せたいと思います。原稿用紙約17枚です。
どうか、読み物嫌いの方は見過ごして下さい。
少しでも読み物好きの方は、暇つぶしにでもしていただければ幸いです。
日記に書いてどうすると考えるのですが、日記は自分自身をさらけ出すところ。
こんなものがあってもいいかなと。
猫が出てこない話なので気が引けますが、何なりとご感想でも頂くと喜ぶと思います。
皆さんから勇気をもらえば、僕達もまた活躍できますからね。
よその作家さんサイトで今までの中では少し評価があったものです。
お暇つぶしにどうぞ。

チップの口内炎は月一の注射でなんとかコントロール出来ています。今は餌もちゃんと食べますが、痛みが出始めるとまた、注射のお世話にならなければなりません。
byホワイト
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「越後屋」
ホワイト著
暗く湿った岩肌に、ところどころに置かれている松明の明かりだけがほの暗く反射していた。
あたりにはひんやりとした空気が漂っている。高い天井からは水滴が落ち、その音だけが庭ほどの広さがある岩穴に響いていた。
中央には岩でできた大きな椅子があり、太い眉毛の筋骨隆々としたひときわ大きな男が厳めしい顔をして座っていた。右側には罪人たちの生前の行いを写す浄玻璃鏡が、左にはこれまた大きな釜があった。
大男は大きな血走った目を見開き、眼前にひれ伏す小男を見下ろしていた。
すでに九人の王による審判を受けてきて、今日が最後の十人目の審判を受ける日であった。
「越後屋と申したな。うぬは現世では非道、悪行を繰り返していたようじゃの」
岩穴に低く太い声が響いた。
「とんでもございません。私はお国の為、お代官様のお役に立つように働いておりました」
越後屋と言われた小男は、額を床にこすり付けたまま消え入るようなか細い声で答えていた。
大男は血走った目をさらに大きく剥き出しにしている。
「黙れ! このわしにしらを切るつもりか。うぬの行いは全てこの浄玻璃鏡で確認しておるわ。この期に及んでも自分がしてきた悪行を反省しておらぬのか」
岩穴が崩れ落ちそうな大声が浴びせられた。
「確かに見方によれば非道な行いに見えるかもしれません。しかし、お国を治めるには多少の犠牲もやむを得ぬ場合があります。お代官様も多くの民を救う為、お国を治める為、覚悟の上での行いと心を痛めておいででした」
一喝に震えながらも、必死で言い訳を申し立てる。
「では、うぬの行いで犠牲になったものは、国を治める為の人柱にでもなったとでもいうのか」
大男の目ははち切れんばかりに剥き出された。
「決して人柱などと。ただただ、全てはお国の為を思い」
越後屋はさらに体を小さくし、声を震わしていた。
「黙れ!」
大きな足を一歩踏み出し、越後屋に覆いかぶさるようにして見下ろした。
振動で岩穴が揺れ、天井からは水滴がいっせいに落ちてきた。大男の背が濡れ、その下で越後屋は恐怖に震えていた。
「うぬはそうして口先で多くの民をたぶらかし、私利私欲を肥えさせてきたではないか。これもお国の為か」
今にも握りつぶしそうな剣幕だ。
恐怖に怯えながらも、何とかこの状況を打開できぬかと言葉巧みに話している。
「とんでもないことです。私には仕えてくれる者も多くおります。また、家に帰れば幼き子供達もおります。みな私の働きによって食べているものです。それを私利私欲と仰せであれば如何様にも申し開きがございません。今まで何の為に汗水流して働いてきたものやら、切のうございます」
ひれ伏した姿勢のままで小ざかしい言い訳を並べてみた。
あきれ果てた大男は大きなため息を吐いた。
腹黒いものを全て吐き出させるためなのか、玉ねぎとにんにくがが腐ったような物凄い悪臭が岩穴に充満した。越後屋は口元を押さえ、こみ上げる激しい吐き気を我慢していた。
「以前、売られてきた娘子がおったな。その後いかがした」
悪臭で吐き気に苦しむ越後屋に満足したのか、大男は怒りを静めて椅子に座りなおし、問いかけてきた。
「はい、あれはいい子でした。売られるにはあまりに可哀想なので、私が引き取ることといたしました」
冷静さを取り戻した大男に少しは安心したのか、余裕が生まれた。
「では、おぬしのところで奉公いたしておるのか」
「はい、別に屋敷を与えまして住まわしております。身の回りの世話と子守りなどをさせております」
「誰の子じゃ」
「はい、拙者の子でございます。あれに似て可愛いややでございます」
「それでは、手篭めにしたのではないか」
「とんでもない。人助けにございます」
強烈な臭気に臭覚が麻痺し、吐き気も治まっていた。
「では、川でおぼれそうになった商人はどうした」
「ああ、あの時は大変でございました。水かさの増した川でしたので岸に引き上げて助けましたのでございます」
「そのときの持ち物はいかがした」
「はい、色々と身に着けていると重たいので先に取り除きました。でないと岸に引き上げれませなんだ」
「持ち物は返したのか」
「いいえ、預かっております」
「それでは追い剥ぎではないか」
「とんでもない。人助けにございます」
こやつには良心の欠片もないのかと情けなくなるばかりで力が抜けてきた。
「庄屋が家事になった時はいかがした」
「はい、一番に駆けつけて火消しを手伝いましてでございます」
「ほう、どのようにしてじゃ」
浄玻璃鏡ですでに越後屋の行いは確認済みである。どのような申し開きをするかを試していたのであった。
「燃えやすい書画などを運び出してございます」
「それをどうした」
「燃え移らないところで保管いたしてございます」
「どこじゃ」
「越後屋の倉でございますが、何か不都合でもございましょうや」
したたかな越後屋は浄瑠璃鏡で見られたのを承知の上で正直者を装っていた。
「それでは火事場泥棒ではないか。何が火消しを手伝ったじゃ。嘘はついておらぬようじゃが許されることではなかろう」
「滅相もない。燃えやすい物を運び出して少しでも火の勢いを治めようとしたのが間違いと仰るのですか。大火を免れたお陰で庄屋は焼け死なずに済みましてございます。これも立派な人助けにございますれば」
やはり口では一枚上手である。怒りをかわしながら自分のペースに引き込んでいく。大男は小賢しい言い方にただ呆れるばかりだった。
「えーい、うぬの話を聞いておっても埒が明かぬは。とっとと地獄へ落ちるがいいぞ」
大男は業を煮やし、ついに見限った。
「落ち着き下され。投げやりになってはいけませぬ。どうせ地獄に落ちる身。腹の中に一物抱えていても浮かばれませぬ。全て吐き出して行きますれば、現世への未練も尽きましょうぞ」
大男は地獄の釜の蓋を手にしたまま見下ろしている。釜の中は真っ赤な液体が煮えたぎり、熱気はひれ伏す越後屋にも届いていた。
「なんじゃ、申してみよ」
越後屋は、熱気にむせ返りながらもこの期を逃してはならぬと必死だ。
「この世には善と悪がございます。しかし、これは誰が決めるのでございましょうや。他人の行いを、その本質を見ることなく偏見で地獄と天国へ振分ける事ほど罪な事がございますまいか。私の行いの何処が間違っておりましたでしょうか。代官様に尽くしていたのを、諸国を旅するという世直し爺に印籠ごときを見せられて、そのまま打ち首とはこれこそ理不尽でございます。そして、あなた様は地獄へ行けと仰せ。どう見ても地獄行きと思われた者が天国にいるとの事が、現世でまことしやかに言われてございました。生前に貢物でもしていたのであろうとの噂でございます。天国での酒池肉林の呆けた者たちの様子、御存知でありましょうや。その証拠にかつては天下の大泥棒と言われた石川何がしは、今では英雄でございます。それよりも拙者は苦しくても生きようともがいている地獄の者たちの方が誇らしく見えます。死ぬことも出来ず、必死に生きるすべを探している姿に心を打たれます。その者たちの叫びが聞こえませんか」
心にもない事をまるで見てきたように嘯いていた。
「では、さっさとうぬも地獄へ落ちて誇らしくしておるのじゃな」
越後屋の危弁には耳を貸そうともせず地獄行きを宣言しようとする。ところが素直に応じるわけがないのだ。あれやこれやと難癖を付けてくる。
「お待ち下され。地獄へ落ちる前に最後に一つだけ望みをかなえては下さいませんでしょうか。世の為、人の為、お代官様の為に精一杯生きてきたのでございますれば」
人の良い大男は耳を傾けてしまった。
「毎年、盛大に村祭りをやっております。御存知でしょうか。たくさんのお供え物、酒、米、村人達が作った団子など届いておりますでしょうか」
「おう、いつも感謝しておるのじゃ。あの団子はうまいぞ」
大男の血走ったむき出しの目が幾分和らいだようだ。
それを狡賢い越後屋が見逃すはずはなかった。作り話にも熱がこもってくる。
「そうでしょう。村人が、それはそれは丹精込めて作っておりますので。その村祭りを支えておりますのが私でございまして」
「さようであったか、ご苦労じゃったな」
最初の頃の威圧が消え、大男は手にした地獄の釜の蓋も元に戻している。
「我が倉の最高の米、酒を惜しげもなく奉納しております」
越後屋はここぞとばかりに大法螺を吹いた。
「しかし、今年からはそれも出来ますまい。あの酒や米は特別なものゆえ保管場所を誰にも教えていませなんだ。今からでも妻の夢枕に立って教えてあげたいものですが、それも叶いますまい」
神妙にかたる越後屋に大男も同情し始めた。いや、祭りで奉納される、酒や団子に未練を感じたのかもしれない。
「では越後屋。長年、村祭りを支えてきた苦労に免じて、最後に一つだけ望みを適えてやろう。何かあれば申してみよ」
欲に目がくらんだのが大きな間違いの始まりだった。
「本当でございますか。本当に叶いますか」
越後屋のひれ伏した顔に胡散臭い笑いが浮かんでいるのを大男は気付くはずがなかった。
「申してみよ。最後に会いたい者でもおれば合わせてやろう。伝えたいことがあれば申して来るが良いぞ。ただし、一回切りじゃ。欲張っていかん。わしが嘘をつくとでも思うてか」
「滅相もございません。では、大変申し上げ難いのですが、閻魔大王になりたいです」
越後屋が言うや否や、驚いたことに目の前にいた閻魔大王が塩をかけられたナメクジのように段々と萎んでいくのだ。
「何を言い出すのじゃ、戯けたことを。妻に米や酒の保管場所を教えるのではなかったのか」
岩穴に轟いていた閻魔大王の声が甲高いか細い声に変わって行く。
「はて、誰がそのような事を申し上げましたでしょうかの。おおー、どうしたことじゃ」
白々しく嘯く越後屋の体はむくむくと筋肉が盛り上がり、大男へと変貌していった。
「やめろ、何をする」
大男となった越後屋は、虫けらのように小さくなっていく閻魔大王を鼻先につまみあげていた。
「すまんの。願いが二回叶うのであればもう一度入れ替われたものを、一度だけしか叶わぬゆえ元には戻れぬでな。握りつぶしたいところじゃが、地獄ではお前さんに落とされた多くの罪人たちが待っていようでな。恨むなよ」
越後屋閻魔はつまんでいる閻魔を振りながら残忍な目で見つめていた。
「それだけは、止めてくれ。殺されてしまう」
小さな閻魔は手足をバタつかせながら訴えていた。
「何言ってんだい。地獄では死なねえよ。いや、死ねないんだよ。お前さんが送り込んだ多くの罪人と同じ苦しみを味わうんだな」
そう言うと地獄の蓋を開けて投げ入れてしまった。
「助けてくれー」
煮えたぎる地獄の釜の中を小さな閻魔が浮き沈みしている。
もがき苦しんでいた閻魔の姿が見えなくなったのを確認して蓋を閉じた。
「やれやれ、てこずらせおって」
岩穴には元の静寂が訪れ、水滴の音だけが響いている。
筋肉隆々になった体を繁々と見つめながら、先ほどまで閻魔大王が座っていた椅子に腰掛けた。座り心地を確かめるようにゆっくりとあたりを見回し、大きく一つ咳払いすると次の罪人を呼び入れた。
「次」
越後屋閻魔の前にひれ伏す罪人。
「顔を上げい」
見下しながら貫禄のない声で告げた。
罪人は想像を絶する大男の閻魔大王がいると思い恐る恐る顔をあげた。
ところが体こそ山のように大きいがそこには不釣合いな胡散臭い顔が乗っている。
口を開けて思わず首をかしげた。
「もしかして、越後屋か。これはどういうことじゃ」
拍子抜けした声で罪人が言った。
「おぬしは、代官ではないか。やはりわしの次に打ち首になったのか」
「あやつは喰えぬ爺だったのう。わしまで打ち首にしおって。それにしてもなんでおぬしがそこにおる」
目の前にいる閻魔大王が越後屋と知って青ざめていた代官の顔に血の気が戻ってきた。態度も大きくなり胡坐をかいて座りなおした。
越後屋閻魔は先程までのいきさつを手短に話した。
「そうであったか。いやはや世の中何が起こるかわからんものじゃな」
代官は現世での威厳をとりもどし感慨深げだった。
「ところで、代官は天国と地獄どちらへ行きたいのじゃ」
「そりゃ、もちろん天国じゃろう。上手い酒もたんとあると聞いておる。良き女子もおるらしいの。それに印籠見せられて打ち首になることもなかろうでな」
「では、天国へ行かれよ。わしはここで裁きをせねばならぬでな。あの爺も長くはなかろうで、ここへ寄った時に地獄へ落としてやるわ。お主には良い子が来れば天国へ送って進ぜようぞ」
越後屋閻魔は口元に意味深な笑いを浮かべている。代官は淫靡な光を湛えた目で越後屋閻魔を見返していた。
「それにしても、越後屋。お主も・・・」
代官はいつもの口癖で越後屋閻魔に言っていた。
岩穴にはいつまでも二人の大きな笑い声が響き渡るのであった。
(おしまい)


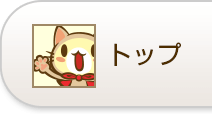
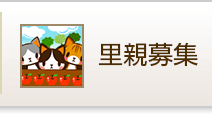



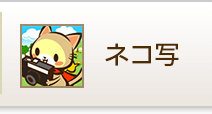

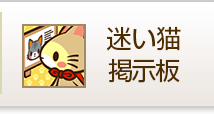
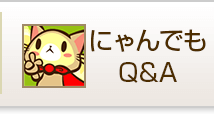











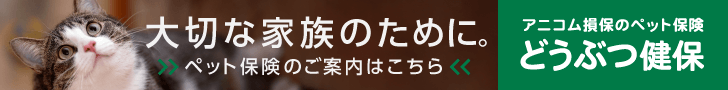
 0
0
最近のコメント