北国は寒い地域だという定説も、1年経つごとにそうでもなくなってきてるんじゃないかと思ったり。
先日、地場産の食材を使った料理教室があって、仕事でお邪魔したんですが、その時にお会いした50~70代の奥様たちから貴重な話を伺いました。
昔…今から4、50年前の津軽地方では、冬は家の2階から出入りしなければならないくらい雪が積もったそうです。当時は冷蔵庫もほとんどなかった時代、冬場は雪を使って冷蔵庫代わりにしていたり、家の外に漬物樽を置いておけば、寒さのおかげで酸っぱくならずに春まで保存できたとか。
今では町のあちこちで出会う除雪車も、「昔はすったもの(そんなもの)無(ね)がったジャ!」
「みんな、家の2階の窓がら出て、屋根まで届ぐンタ雪ゴト踏み締めで、固めで、道作って歩いたんだ」
わたしが小さかった頃も雪は多かったと思ったけど、その頃の10倍以上は雪が降っていたんだと思います。
当時の人々の暮らし…雪深い地域ごとにスーパーがあったわけでもないので、食材は秋の収穫後にほとんど干すか、漬物などに加工して、冬場はそれらを水で戻したり、焼いたりして食べていたそうです。
奥様たちは「昔の生活って、そったものだったのサ~」と笑って言うけど、同じ生活をやってみるとしたら、わたしはたぶん出来ません…
常に暖かい家、食材を保存できる冷蔵庫、除雪車、スーパー、などなど…
今のわたしたちの暮らしはなんと裕福なんだろう!
津軽の女性を、我慢強い、忍耐強い、芯が通っている、なんて表される事があります。
それは、過酷な寒さと雪に耐えて暮らし、春から秋には米や野菜作りのために夫と同じかそれ以上に働き、子供を育ててきた、彼女たちのことを差すんだ、と奥様たちを見て、感じたのでした。
さて、津軽の冬の象徴「ストーブ列車」の運行が1日から始まりました。

あいにく逆光で見えづらいけど、ストーブ列車の先頭です。
ストーブ列車を走らせているのは、青森県五所川原市と中泊町の南北をつなぐ私鉄、津軽鉄道。

ストーブ列車が津軽鉄道を走るようになってから、何年経っているでしょう?
答えは…80年!
ところどころ、修理を重ねながら、大事に大事に運行されてきました。
このストーブ列車が何代目なのかは分かりませんが、とっても古いです。

ストーブはこちら。
石炭を燃やして、車内を暖めます。スルメも焼けるし、お餅だって、オニギリだってOK!
昔も今も数多くの乗客が、ここで色んなものを焼いて食べながら、車窓を楽しんでいます。
上記の料理教室で出会った奥様が、このストーブ列車でたった一度しかなかった出来事に遭遇していました。
奥様が19歳の頃、帰宅するためにストーブ列車に乗ったら、猛吹雪で列車が立ち往生!
運転手たちがスコップ片手に列車の周りの雪を片付けても片付けても、雪はどんどん積もるばかり…
ようやく列車が動き、終点の津軽中泊駅に到着し、彼女が家に着いたのは夜中の2時!
タクシーも車もなく、携帯だってないし、電話も近くにない時代。吹雪と深雪の中を歩くこともできず、彼女は列車が進むのを車内でひたすら待ち続けたそうです。
津軽鉄道の列車が止まったのは、後にも先にもこの一度だけ。
すごい出来事を体験した人と出会えたわたしは、なんとも言えない心の震えを覚えたのでした。


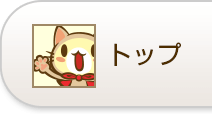
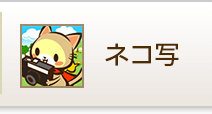

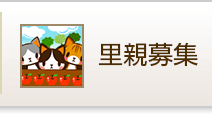
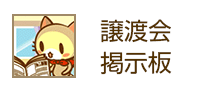


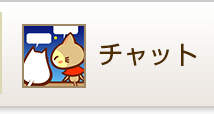
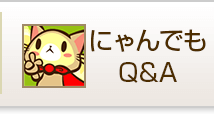
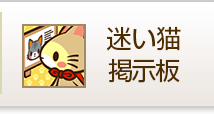
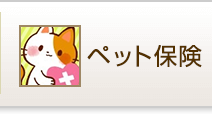
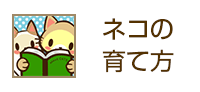
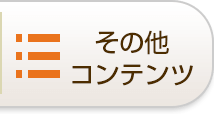

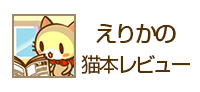
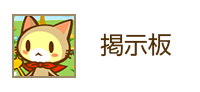




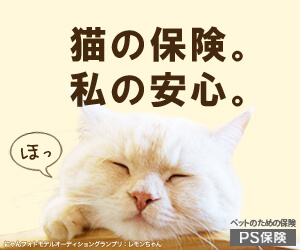


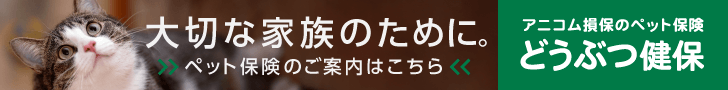
 0
0
最近のコメント