「僕は、気がついたときにはもう一人ぼっちさ。でも、寂しくなんかなかったよ。お母さんを知らなくても寂しくなんかなかったよ。だって思い出なんて何にもないから。一人でいるのが当たり前だったから」
そう話し始めるチップだった。
「お母さんだって、僕の事など心配していないにきまってるさ。僕は気ままに生きてきたよ。好きなところに行って、好き
な事をして」
気丈に明るく話すチップを見て、おばさんの頬には光るものがあった。
チップは、高台にある高校の近くで暮らしていた。
どうやってそこへ来たのか。いつから居るか自分自身でも記憶がない。
ただ、そこにいる限り食べ物には困らなかった。気付いたときはすでに暮らしていた。
高校生は、お弁当の中で嫌いな物は親が一生懸命作ってくれたものでも平気で残す。ただ、さすがに持って帰るのは気が引けるのだろ、空腹そうにしている猫たちに与えて帰るのだ。
猫たちもおりこうにしているとお裾分けに預かれると知っていた。高校生の好き嫌いが野良猫たちを助けていたのだ。
そんな中の一匹がチップだった。ところが定期的に彼らにも困った問題が起こるのだ。
それは、学校が長期の休みになるときだ。一番長い夏休みは辛かった。学生がいなくなり、当てにしているお弁当の残りがもらえないからだ。
チップも夏休みになって、空腹を我慢し切れずに高校のそばを離れて近くの商店がある方に下りてきた。少しでも人通りがあれば何かの食べ物にありつけるだろうと考えてだ。すでに、高校生との触れ合いで、どのようにすれば人間が気を許してくれるかを熟知していた。
人の出入りが多そうな店の前に行っても決して悪さはしなかった。ひたすら我慢して、毎日同じ時間に、同じ場所で横になった。ただ死んだように横になり日向ぼっこをするだけだ。しばらくすると去っていく。来る日も来る日も。たまに本当に死んでいるのではないかと心配して、かがみ込んで見て行く通行人もいた。
店の主人は何の悪さをするわけでもない猫をお客さんの手前、追い払えないでいた。相変わらず冷たい目で見下ろすだけだった。
しかし、こう毎日同じ事をされていては店の主人も気にしないわけがない。
すると不思議な事に、主人の目が次第に優しさを帯び始めてきたのだ。決して餌をくれたりすることはなかったが、登場するのが遅いと心配して待っているようになった。表に出て、来ていないかキョロキョロ探している。そんな時も、チップは何食わぬ顔でいつものようにさり気なく近づき、いつもの場所で横になる。主人の心を掴みかけていると分かっても、小走りに近づいたり、足元に擦り寄ったり、決してしなかった。空腹を我慢して、淡々と毎日を過ごした。
そうして二週間ほど経ち、お盆休みになった時、運命の日がやってきた。
人通りがなくなり、誰も来ない店先にいるのは寂しいだろうと、主人はとうとう家に連れて帰ってしまったのだ。ペットが居なかった家では子供達が大喜びした。見かけは多少悪くとも子供たちに取ってはよその家庭と同じペットだったのだ。すぐにチップという名前をもらい、餌を与えられた。首輪も付けてもらった。家族になった証だ。家族みんなで可愛がってくれた。猫嫌いだったことが信じられないほど主人も可愛がり始めた。保護してもらった時の体重は二キロに満たない位だった。ほとんど骨と皮だけの状態であった。良くこんな状態で生きていたなと主人は感心していた。
それからひと月もしない時に新たなお客さんが来た。
朝、主人が窓を開けベランダを見ると、そこに真っ白で青い目をした片手に乗るほどの仔猫がいたのだ。母猫にはぐれ、行き場のなかった仔猫がベランダで夜を明かしたようだ。
とても野良とは思えない可愛いらしさだった。真っ白い体からホワイトと名前を付けられて一緒にお世話してもらうことになった。
多分生まれて二ヶ月もなっていなかっただろう。
ところがホワイトには生まれつきの障害があった。
外見上は普通にしていたため、人間たちは誰も気付いていなかった。
しかし、同じ猫として、チップだけはすぐに見抜いていた。
ホワイトは生まれながらに耳が全く聞こえていなかったのだ。母猫の元へ帰ることが出来なくなったのもその為かもしれない。いくら母猫が探して呼びまわってもその声が聞こえなかったのだろう。
チップは耳が聞こえないホワイトに、トイレの仕方やグルーミングを教えてやった、親代わりになって。ホワイトもチップのことを本当の親のように懐いた。二匹はいつも寄り添うようにして寝ていた。
血はつながっていなくても、本当の親子以上の絆は出来るものなのだ。たとえそれが猫であっても。
チップはもう一人ぼっちではなくなった。家族が出来たのだ。親代わりとして慕ってくれるホワイトがいる。
ホワイトもチップがいることで寂しい思いをせずにすんでいた。一年後にはチップと同じ大きさになった。二匹とも五キロ近くまで成長していた。同じオス同士でありながら実に仲の良い二匹だった。成長したホワイトとは親子というより仲睦まじい夫婦のようにも見えた。
こうしてチップは生涯の残りを、ホワイトはそのほとんどを家猫として幸せに暮らすことが出来た。
幸せな日々は五年近く続いた。
しかし、野良猫として幼少時代を過ごしていたチップの体には、過酷な生活を物語るように様々なダメージが蓄積していた。
歯はボロボロ、足の骨は曲がったまま繋がっている。ついには口の中が赤くただれ始め、痛みで水さえ飲めないほどになった。
注射で何とか痛みを抑えてもらったが、だんだん効かなくなり、高齢になったチップは内蔵へも負担がきていた。
そして、ある晩、大好きだったホワイトの横で、家族みんなに見守られて生涯を閉じた。
野良のままであったら決して味わう事のできなかった暖かい
家庭、家族の温もりを感じながら静かに橋を渡っていった。
「でも僕が亡くなって、ホワイトは寂しがっていると思うんだ。僕より五歳以上も若いし、まだまだ長生きできるもの。だから、ホワイトが亡くなって橋を渡って来るまで待っていたいんだ。だってここへ来て一人ぼっちじゃ可愛そうでしょう。きっと僕に会えたら喜んでくれるはずさ。それに、ここでは現世での怪我や病気が治るのでしょう。ホワイトの耳も聞こえるようになると思うのさ。再会出来たら僕の声を聞かせてあげるんだ。ホワイトって呼んでね」
チップの瞳は希望に輝いていた。
「おばさんも一緒にいようよ。行方不明の子供に出会うまでみんなと一緒にいようよ」
チップは自分の半生を語り終えおばさんを見ている。
「ええ、私も行方が分からなくなった子に会うまでは一本松にいるつもりでした。でもね、その必要もなくなったのですよ」
おばさんは座ったまま遠くの空を見上げている。
つづく
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
さあ、いかがでしたか。今回のお話。
これはチップが我が家に来たときのお話を基に想像したものです。
以前書いた「ゲンさん奮闘記」につながる内容です。
話をもっと長くしようかと思えば、合体させると尺の長いものになります。でも、そうすると橋の向こうでの出来事に対してインパクトが薄らぐような気がし、このくらいの長さにまとめました。
さて、次回は母猫のちょっと辛い過去が出てきます。あまり深刻にならない程度に書いたつもりです。
でも、こういう現実もあります。どうか改善できる方向に進めば良いと考えます。これは全ての猫好きさんの願いのはずです。
どうか次回もお付き合い下さい。

やっと僕の出番がきました。それにしても少ないですね。
By ホワイト


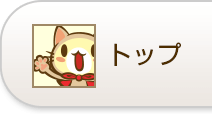
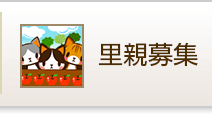



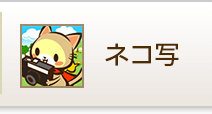

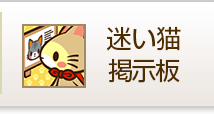
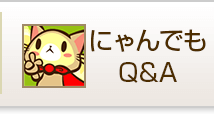











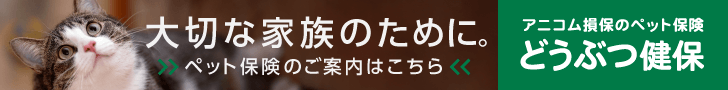
 0
0
最近のコメント